Notices(通知)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNotices(通知)があります。
これは,例えば,契約の解除など重要な意思表示の通知については,通常契約書において「書面によりなされる」(in writing)と規定されている場合が多いところ,その書面による通知をどこに出すのかを決めておくことがメインになる条項です。
通常は,当事者の本店所在地の住所,代表取締役宛と定められることになります。他に支社がある場合や,代表権を有する者が複数いるような場合は,未到着などの主張を許さないよう,どこの誰宛に送れば良いのかを決めておくほうが安全です。
また,書面を出したが,配達記録が届かないなどの事態を防止するため,英文契約書のNotices(通知)条項では,発送を証明できる場合は,「配達記録に書かれた日か,発送からX日後のいずれか早い日に到達したとみなす」と規定することもあります。
これにより,遅くとも配達からX日後に相手方に書面が到達したことにできるというわけです。解除の意思表示や,更新拒絶の意思表示はとりわけ重要な意思表示となりますから,相手方の受領していない,知らないなどの「言い訳」を防ぐために対応は慎重になされるべきです。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Entire Agreement(完全合意)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Entire Agreement(完全合意)条項があります。
英文契約書によく登場するこの条項の意義・趣旨は以下の点にあります。
本体の英文契約書の締結に至るまで,当事者は色々な手段で,交渉・通信をしているのが通常です。
面会,電話,Eメール,SNS,FAX等を用いて,最終的に契約に至るまで,交渉を何ヶ月にわたって,ときには何年も継続することもあるでしょう。
このように交渉では長期にわたり何度もやりとりをするので,最終的に締結することになった契約書の条項の内容と矛盾・衝突するような内容もあるかもしれません。
また,場合によっては,英文契約書の内容とは違う説明をEメールや電話で受けるかもしれません。
例えば「契約書にはこのように書いてあるけど,実際にはかくかくしかじかなので大丈夫ですよ」などという説明です。
当然,大原則は,あくまで英文契約書に書かれた内容を解釈することになるのですが,場合によっては,Representationなどの理論によって,契約書外の通信や説明内容が契約書の解釈に影響を与える場合があります。
当事者の一方が,「契約書と異なる説明がEメールに書かれているから,Eメールのほうの内容に納得してサインしたのだ」と主張したいという場面を想起すればわかりやすいでしょう。
原則として,このような主張を退けたいがために規定するのが,Entire Agreement(完全合意)(エンタイア・アグリーメント)条項です。
したがって,通常,英文契約書にある同条項の内容は,「本契約に書かれた内容が当事者の最終的なすべての合意内容を表すのであって,これ以外のあらゆる方法による合意内容,交渉内容は本契約の締結をもって失効する」という旨が規定されています。
特に交渉過程で内容が変遷したり,交渉期間が長く,LOI(Letter of Intent)/MOU(Memorandum of Understanding)などを覚書として交わしている契約では重要な意味をもつ条項といえます。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Amendments(改定)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Amendments(改定)条項があります。
これは,概ね次のような内容になっている場合が多いです。
「本契約の内容を変更・改定する場合は,各当事者の権限ある者が署名した書面によってのみ行うことができる。」
このような条項を入れる目的は,先のEntire Agreement(完全合意)条項にも絡むのですが,基本的に当該英文契約書以外の約束や合意の効果を排除したいという点にあります。
英文契約締結前にかかわらず,英文契約締結後でも,当事者が「契約書にはこのように規定されているが,その後電話で・・・と合意している。だから,後の合意が優先するはずだ。」などと主張する場面をなくそうという点に主眼があります。
多くの国が,契約や合意の効果は,特に書面にしなくとも口頭によっても生じるとしています。
したがって,一旦契約書を作成しても,その後に口頭で契約書と異なる内容を合意すれば,基本的には,時系列上新しい合意が優先しますから,後者の口頭合意が優先することになります。
ただ,このような原則は,書面になっていない以上,口頭によるそのような合意があったのか,なかったのか,あったとしてどういう内容だったのかについて紛争を生じやすいと言えます。
そのため,このような事態を避け,常に書面による合意によって契約内容を改定すると合意しておくのです。
このAmendments(改定)条項は,ほとんどの英文契約書に見られる一般条項なのですが,挿入されていた場合,注意しておいたほうがよい場面があります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの基本契約を締結し,その契約に基づいて,個別の売買が発注書と受注書を交わすことにより成立するというパターンがあります。
この場合に,基本契約である販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の内容と異なる内容で発注書と受注書を交わし,その個別売買だけは基本契約の内容と違う内容で成立させたいということがあったとします。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に,個別契約と本契約の内容が矛盾する場合は個別契約の内容が優先するという条項があれば,個別契約の内容が効力を有するので問題ありません。
ただ,上記のような条項がない場合,個別契約の内容を優先できるかというと,このAmendments(改定)条項があるので,個別契約の内容は効力を有しないという解釈になる可能性が高いので注意が必要です。
Amendments(改定)条項を入れる意味は,現場の担当者が勝手に基本契約の内容を変更できないように,権限者の署名ある書面が必要としているところもあるので,このような解釈になるのはやむを得ないでしょう。
したがって,もし個別契約については例外的に優先するとしたいのであれば,きちんと契約書に書いておくのが安全ということになります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Severability(分離/可分性)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Severability(分離/可分性)条項があります。
この条項は,日本語の契約書ではあまり見ない印象です。
内容としては,「本契約に定める1つ以上の条項が,管轄裁判所の判断により無効とされることがあっても,その他の条項は影響を受けず,有効なまま存続する。」というものが多いといえます。
さらに詳しい内容の場合は,上記内容に加えて,さらに「無効となった場合は・・・両当事者が当該無効となった条項により達成しようとした内容に最も近い内容で,かつ,準拠法により適法・有効である内容に自動的に変更される。」という旨の規定があることもあります。
日本法が準拠法となる場合,このような条項がなければ,英文契約書の一部の条項が無効となった場合に,英文契約書全体が無効,または,その他の条項も含めて無効となるのかというと,通常そういうことはないでしょう。
ただ,条項の違反の程度,違反の性質によっては上記事態もありうるでしょうし,当事者の意思としてあくまで契約を続ける意思が根底にあるのだと示しておくことには,条項解釈などの上で意味があると思います。
英文契約書は,異なる法体系を有する企業が英語で締結する場合が多いため,最終的にどのような理論で誰が契約条項の解釈をするのかが,国内契約よりも想定しにくいという特徴があります。
したがって,当事者がどのようにしたいと考えているのか,事細かく英文契約書に記載する姿勢は基本的には歓迎されるものだと思います。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Relationship of the Parties(両当事者の関係)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Relationship of the Parties(両当事者の関係)条項があります。
これは,通常,「両当事者は,独立した契約者であって,他方の代理人ではない。他方当事者が本契約に関して,または,本契約に関せず行ったいかなる行為も相手方当事者にその法的効果が帰属することはない。」という内容を含んでいます。
例えば,販売店契約などを結ぶと,指名を受けた販売店が,メーカーの製品を販促し,契約を取り付けて広く販売をしていくことになります。
このような活動中,販売店としては,メーカーのロゴや商標,ブランドを使用してよいというライセンスを得ていることが一般的です。そのため,製品の販促や販売過程で,取引先が販売店を直営店や代理店と誤解する場合も考えられます。
そのようなときに,あくまで契約当事者の間では,販売店はメーカーを代理する権限を有するものではなく,販売店の行った行為による法的効果はすべて販売店に帰属することを確認したいがために挿入する条項です。
なお,英文販売店契約書にこのような条項を定めたとしても,取引先が,当該行為をメーカーの行為だと信じた場合に,法的効果がメーカーに帰属することは,各国の法律,その行為の状況などによりあり得ます。
あくまで,この条項に拘束されるのは英文契約書にサインした当事者,つまり,メーカーと販売店だけなので,第三者との関係は法律によって規律される場面がありうるためです。
その場合は,このことによってメーカーが対応せざるを得なくなった場合のコストなどを,販売店側に課せるかどうかという問題になります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Language(言語)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)
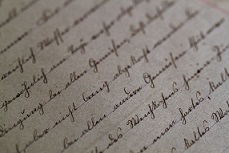
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Language(言語)条項があります。
これは,例えば,日本語を理解せず,英語を理解する取引先と契約を結ぶ際,取引先は日本語の契約書を締結することには承諾しているが,英語の翻訳文をつけて欲しいという要望があるような場合に検討を要する条項です。
このような場合に,単に,日本語と英語の両方を契約書に載せて契約をするのは危険です。
なぜなら,日本語と英語はあくまで別の言語ですから,いくら原文に忠実に翻訳したとしても,やはり完全に一致させることは不可能であるところ,仮に契約条項の解釈をめぐって紛争になったような場合,いったいどちらの言語にしたがって,意味内容を解釈すればよいのか直ちに判別できなくなってしまうからです。
このような事態を避けるためには,どちらかの言語で契約をする(上記例では日本語)ということは事前に決定し,もう一つの言語はあくまで参考にすぎない(上記例では英語)ということを契約書に定めておくことが重要です。
よくある例は,「本契約は日本語で締結されるものとし,本契約書に添付された英語の翻訳は,あくまで参考のために添付されたものに過ぎず,英語の翻訳は当事者を一切拘束しない。」などと規定されます。
日本語と英語のどちらが拘束力を持つと規定すべきですかという質問をよく受けますが,日本語のほうが良いと思います。
このパターンでは,もともと和文契約書があり,それを英訳して英文契約書ができあがっていることが多いです。
この場合,日本の商慣習と法律にしたがって作られていることがほとんどなので,やはり和文が優先するとしたほうが適切です。
いざ紛争になったときも,母国語として対応できる言語で作られているほうが誤解もありません。
また,日本の裁判所は日本語の証拠しか受け付けませんので,その点からも日本語の契約書が拘束力を持つとしておいたほうが適切です。
もっとも,相手が日本語を全く読めないのに,無理に和文契約書を締結させたというようなケースでは,紛争になった際に,「日本語が全くわからないので英語での契約を何度も主張したのに,無理に和文契約書で締結させられたから,無効だ」などと主張される可能性が高まるかもしれませんので,注意が必要です。
さらに,契約書の準拠法が外国法になっていて,紛争時の裁判の管轄もその外国になっているようなケースの場合も検討を要します。
外国法が適用される場合,和文の契約書を逆に外国語に翻訳することになると思いますが,その翻訳が,先程の例とは逆に,ニュアンスや内容を取り違えて裁判所や相手方に伝えてしまうリスクがあります。
そのため,準拠法が日本法で,紛争解決も日本で行うとされている場合に限って和文契約書を作成するというのも合理的な方法だと思います。
いずれにせよ,契約書の内容は紛争時に非常に重要な証拠になりますから,どの言語を選択するにしても,誤解されやすい内容,多義的な内容,あいまいな内容は極力避け,明瞭でわかりやすい契約書にするのが何よりも大切になります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
No Waiver(放棄の否定)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNo Waiver(放棄の否定)条項があります。
これは,英文契約書で使用された場合,通常,「各当事者が,本契約に基づきある権利を取得した場合に,これを一定期間行使しなかったからといって,当該権利を放棄したものとはみなされない。」という趣旨で規定されます。
日本も含め,各国の法律で,通常消滅時効という制度が設けられています。ある権利を行使しないまま法律が定める一定の期間が経過すると,一定の要件の下で,消滅時効により権利が失われてしまうというものです。
英文契約書での本条項は,この時効に関して規定しているのではなく,当事者が自らの意思で権利を放棄する場面を想定しています。
権利は,義務と異なり,権利を有するものがその権利を行使するかそれとも行使しないか,または,放棄するかは自由意思に通常委ねられています。
こうした前提で,権利を保有するものが,その権利を相当期間放置して行使しなかった時に,黙示的(明確にそう意思表示があったわけではないが言動などからそのような意思を暗黙に表示したと認められること)に当該権利を放棄したと判断されることのないように,注意的に規定することにその主要な意図があります。
これは,英米法のEquity(衡平法)における「権利の上に眠っているものは保護に値しない」というdoctrine of lachesの概念を意識して置かれているものでもあります。
Lachesというのは「懈怠」というような意味で,「権利を持っているのにそれを合理的な期間内に行使しないのであれば,もはや権利行使はできなくなる」という考え方です。
このlachesの適用を排除したいがためにNo Waiver条項が入れられているとも言えます。
ただし,No Waiverを入れておけば常にlachesの適用を排除できるということでもないので,注意が必要です。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Headings Reference Only(見出しは参考)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Headings Reference Only(タイトルは参考に過ぎない)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約に定められた各条項の意味は,本文に書かれているとおりであり,各条項の冒頭にあるタイトルは,参考のためにあるに過ぎない。各条項の意味に争いが生じたときは,タイトルではなく,各条項の記載内容でその意味を決定する。」などと規定されます。
英文契約条項の意味について当事者間で紛争が生じた時に,裁判所などが採用する解釈手法は様々あるのですが,そうした具体的な話からは離れて,例えば,条項のタイトルと条項内容の具体的記載が合致しない,または,全く違う場合にどうするのかというのがここでの場面です。
具体的な場面ではあまり想定できないでしょうが,No Warrantyなどとタイトルには書いてあって,実際には,The Seller warrants...として保証内容が書かれていた場合を考えてみます。
この場合に,売主は,「具体的条項の内容は,交渉過程で不当に挿入されたもので,タイトルのとおり,本来保証はないはずだ。」などと主張したい事情があったとします。
そうは言えませんというのがこの条項です。ドラフトを作成する法務担当者の方は,以前のデータを利用したりして,つい,タイトルを変えるのを失念して,内容が合わない・・・などという経験があるかもしれません。そのような場合にはありがたい条項と言えるかもしれません。
もちろん,タイトルと内容がリンクしてこうした問題の起こらない英文契約書をドラフトするのが重要であることは言うまでもありません。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
No Assignment(譲渡禁止)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNo Assignment/Successors and Assigns(譲渡禁止/承継人および譲受)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「いずれの契約当事者も,書面による相手方の事前承諾無い限り,本契約上の地位または本契約上の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対し,譲渡,貸与または担保に供することはできない。」などという表現で登場します。
準拠法によっては,契約上の地位や権利義務の移転を,原則許しているということがありえます。そのような場合は,敢えて禁止することを当事者間で合意しなければ譲渡ができることになってしまいます。
既に具体的に生じた金銭債権などであれば問題ありませんが,契約上の地位そのものの移転であったり,何らかの行為を行う,サービスを提供するという「なす債務」の義務を勝手に他に譲渡してしまうことができれば,何のために当該当事者に委託したのかわからなくなってしまうということがありえます。
英文契約書では,一定の条件の下で,譲渡を許すと規定することもあります。もっともポピュラーなのは移転を許可する場面を個別具体的に後で判断するということにし,「相手方の事前の書面による承諾がない限り」としておくことです。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Force Majeure(不可抗力)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Force Majeure(不可抗力)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自然災害,戦争,ストライキ・・・など当事者の合理的なコントロールを超える不可抗力により本契約上の債務の履行ができなかった場合,当該当事者はその債務の不履行または遅滞について責任を負わない」などと規定されます。
英文契約締結後に,当事者の責めに帰すべき事由ではない不可抗力によって債務の履行が不可能になると,後発的履行不能(コモンローではFrustrationという概念に相当します)という問題になります。
このような場合に,予め当事者に責任がないこと,不可抗力による履行遅滞・履行不能の場合にどのような効果を生じるかなどについて定める条項がForce Majeure(不可抗力)です。
不可抗力事由が相当期間継続する場合に,履行できない債務についてどのようにするかについては,例えば,「不可抗力事由が2ヶ月間継続する場合,相手方当事者は,当該契約を解除することができる。」などと規定することもあります。
そうしないと,例えば,英文売買契約において,売主が不可抗力により目的物を引き渡せない状況が長く継続するようなことがあった場合,売主は不可抗力条項により遅滞責任を負わないまま,買主としては目的物の引渡しを延々と待たなければならないという不都合な事態になりかねません。
他にも,英文契約書では,不可抗力事由の通知義務,不可抗力から脱するように努力する義務などを課すこともあります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
No Third Party Beneficiary(第三者へ利益の無供与)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにNo Third Party Beneficiary(第三者への利益の無供与)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約は契約当事者間の権利義務を規定したものであり,第三者に対して如何なる権利や利益を付与することを意図したものではない。」などと規定されます。
英文契約書にこのような条項が挿入される事情は概ね以下のとおりです。
契約の拘束力は,あくまで契約書に署名した当事者にのみ及ぶというのがコモンローでも日本法でも大原則(Privity of Contract)です。
こちらでPrivity of Contractの原則の詳しい解説がご覧頂けます。
ただし,この原則には例外があり,例えば,契約書に,契約当事者以外の第三者の利益のために一方当事者が何らかの義務を履行すると定めたとします。
そうすると,一定の要件の下,この利益を受ける第三者が,義務履行を約束した契約当事者に対して直接その義務の履行を請求できるという効果が生じる場合があるのです。
日本では「第三者のためにする契約」,「受益の意思表示」などと議論される場面です。
英国法でもRights of Third Parties Act 1999がこのような場面を規律しています。
そのため,英文契約書上,あくまで契約当事者間の権利義務を規定したもので,第三者に何らかの権利や利益を付与したものではないことを明確にするためには,このような条項を挿入しおいた方が無難ということになります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Confidentiality(守秘義務)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つとして,Confidentiality(守秘義務)条項があります。
なお,英文守秘義務契約は,Confidentiality Agreementと呼ばれたり,Non Disclosure Agreementと呼ばれたりします。
契約交渉のステージが相当期間ある場合や,一定の契約の類型の場合には,本体の契約を交わす前にこれらの英文守秘義務契約書を交わし,その上で交渉を重ね契約に至るという流れがよく見られます。
このような事前の英文守秘義務契約書を締結するか否かにかかわらず,本体の契約を締結する段階で守秘義務条項を定めることがよくあります。
内容は様々ですが,①守秘義務の対象となる機密情報の定義と範囲,②機密情報に該当しない例外,③機密情報の取扱いについての義務,④契約終了時の機密情報の取扱いについての義務などが定められることが通常です。
ほかにも,①機密情報の指定の仕方,②機密情報の開示可能範囲(自社従業員,取引先,下請業者など),③機密情報の例外の証明の仕方(自社で独自に開発をしたため例外にあたることなどをどのように証明するか),④契約終了後いつまで守秘義務を負うのかなどについて曖昧さを残さず英文契約書に規定しておくことがトラブル回避の基本です。
どのような範囲で情報利用と開示ができるのかは,自社がエージェントやブローカーの立場であるというような場合にはより気をつけなければならないと言えるでしょう。
機密情報は,不正開示によって当該企業の無形財産の価値に大きな損害を及ぼすことがあり得ます。
そのため,守秘義務条項に違反した場合は,違反当事者は損害賠償義務のみならず,差止請求など法令で認められるあらゆる制裁を受けることを承諾するという内容が書かれることもよくあります。
このように英文契約書の条項で取扱について詳細に取り決めることが重要なのはもちろんですが,そもそも自社の機密情報の管理体制についても万全なものとしておくことが肝要です。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Limitation of Liability(責任制限)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Limitation of Liability(責任制限)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,契約当事者が契約違反等により相手方に損害賠償をしなければならないような場合に,その賠償額など,責任を一定限度に限定する場合に使用される条項です。
英文契約書において,責任をどのように制限するか,どの程度に制限するかはまさにケースバイケースですので,その他の一般条項より定型性は低い条項と言えるでしょう。
英文売買契約などでよく見られるのは,例えば,「商品の欠陥や商品の引渡しの遅延などにより買主が損害を被った場合でも,売主は買主に対し,受け取った商品の代金を賠償額の限度として,それを超える部分は免責される」というような,受領した商品代金を責任限度とするという責任制限条項です。
もっとも,このようなLimitation Liability(責任制限条項)は,準拠法によっては無効となったり,効果を制限されてしまうことがありますので,注意が必要です。
取引の実体に即して考えた場合に,余りに売主に有利で,買主に不利益な責任制限条項は無効化してしまうことがあり得ますから,バランスを考えつつ定めることが必要です。
また,Limitation of Liability(責任制限)条項がどの損害に適用されるのか,免責の範囲を確認することも大切です。
例えば,Confidentiality(秘密保持義務)やIntellectual Property(知的財産権)の侵害がないことの保証条項などに違反した場合も責任制限が適用されると問題があります。
これらの義務違反は損害が高額になる可能性があるのに,現実に生じた高額の損害を支払う必要はなく,Limitation of Liability(責任制限)条項に記載された上限額の賠償だけすれば良いとなってしまうと損害を被った側に非常に不利になります。
極端なことをいえば,Limitation of Liability(責任制限)条項に記載された上限額を支払いさえすれば,相手方の機密情報を自社に有利に別の目的で使っても良いと解釈されるおそれがあるのです。
安い金額で相手の機密情報を買って自由に使えてしまうというような極端な解釈ができる可能性があることになってしまうわけです。これはかなり不合理なことがわかるかと思います。
そのため,秘密保持義務や知的財産権の侵害がないことの保証違反の場合は,Limitation of Liability(責任制限)の適用はなく,現実に生じた損害の全額を賠償しなければならないと規定することが多いです。
また,行動経済学で言うところの「アンカリング効果」にも注意が必要です。「アンカリング効果」とは,先に提示された情報や数字に無意識に判断を歪められてしまう認知バイアスをいいます。
例えば,ある商品が元々「1万円」の定価で販売されていたとします。その後,セールで「30%オフ」の価格が提示されると,消費者は「元々1万円だった商品が30%オフで7000円になる」と考えます。このとき,元の価格1万円が「アンカー(基準点)」となり,その後の7000円が割引価格として非常にお得に感じられるというバイアスが生じているとするものです。
例えば,賠償上限を「10億円とする」などと定めた契約書に関して賠償問題が生じ当事者が交渉の場についたとした場合,そのケースでは実際の損害額を計算すればせいぜい1億円程度であったとしても,10億円がアンカーになって,1億円よりもかなり高額な金額で和解が成立する(提示された10億円に交渉心理が影響を受ける)ということがありうるということです。
したがって,上限を定めたほうがよいのかどうかは,一律に考えるのではなく,実際に事故が生じた場合の現実的な損害額を想定し,上限額がその想定より乖離しすぎていないか,生じうる損害額に大きなばらつきがないかなどを考慮して判断するのがよいかと思います。
また,上限額が定められていても,アンカリング効果を意識して上限額に影響されず,想定される実損や判例などを基準に交渉していくことが大切です。特に弁護士をつけずに交渉するときは注意が必要です。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Counterparts(副本)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Counterparts(副本)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約書は,複数の副本により締結することができ,各副本はいずれも正本とみなされ有効であり,全部が一緒になって一つの契約書を構成する。」 などと規定されます。
目的としては,国際取引では,署名者が遠隔地にいることが想定されますので,それぞれの署名者がばらばらに署名しても有効(署名した各1通がCounrterpartとなります。)とする点にあります(要するに同じ紙面に当事者が署名する必要はないということです。)。
特に,クロスボーダー,国際取引では,契約書を締結するとき,Emailでスキャンしてやりとりしたり,ファクシミリでやりとりして締結したいという要請があると思います。
このようなときは,英文契約書に,更に「本契約書は,Emailやファクシミリの送受信によっても締結することができる。」という旨の規定が入ることもあります。
英文契約書に複数副本が作成されると書かれていても,通常は,当事者の数に相当する通数の契約書を用意し,各契約書に当事者全員がサインし,それぞれの当事者が一通ずつ保管するというのが通常です。
このあたりは,日本国内の取引の慣行と相違ありません。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Governing Law(準拠法)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Governing Law(準拠法)条項があります。
クロスボーダー・国際取引では,必然的に2国以上にまたがる当事者が契約に参加するため,契約に関する問題が生じた時に,どこの国の法律を適用して解決するのかということが問題にならざるを得ません。
一般的な2者の当事者での取引の場合,どちらかの国の法律を準拠法にする場合が多いですが,場合によっては中立国の第三国に設定されることもあります。
例えば,日本企業とドイツ企業との取引であれば,日本の法律かドイツの法律が選択されることが多く,場合によって第三国であるスイスの法律などが選択されることになります。
当事者間でどこの国の法律を適用することとするかは,いわゆるBargaining Position(バーゲニングポジション)という当事者の力関係によって決まる場合が少なくありません。
英文契約書において準拠法が外国になると,せっかく規定した契約書の内容が場合によって修正されたり,無効となったりする可能性がありますので,重大な問題といえます。
したがって,準拠法と紛争解決方法,裁判管轄については,他の条項と絡めてしっかりと交渉の舞台に乗せる必要があると言えます。
一般的には,自社が所属している国の法律を準拠法とすることを主張することが多いと思います。
そのため,当事者双方が自国の法律を準拠法とすることを主張し,交渉が平行線をたどり,契約締結ができないということになることも多いです。
ただ,この準拠法は実際には紛争解決条項(裁判管轄・仲裁地)とセットで考えることが通常です。
そのため,必ずしも自国の法律を準拠法にしたほうが有利とは限りません。理由は以下のとおりです。
例えば,日本企業がドイツ企業に対して売掛金の請求について法的手続きを取る可能性があるという取引の場合に,日本法を準拠法とし,裁判管轄を東京地裁としたとします。
この場合,もしドイツ企業が売掛を支払わず,訴訟をしなければならないという場合,日本企業は東京地裁に訴えて,勝訴判決を得ます。
ところが,ドイツ企業が任意に払わないので,この日本の勝訴判決をドイツで強制執行しなければならないということになった場合,ドイツで判決を取得した場合に比べて非常に大変になるわけです。
こうしたことを考えると,最初から契約書で準拠法をドイツ法とし,裁判管轄をドイツの都市の裁判所としておいたほうが適切であったということもあるのです。
なお,英文契約書に準拠法が書いてあれば,一般的に考えて諸外国で尊重されると考えてよいですが,国によっては,否定される可能性もあります。結局は,当地の裁判所等の判断によると言わざるをえないのです。
もし,契約書で準拠法を定めていなければ,基本的に国際私法・抵触法(Conflict of Laws)という問題になり,紛争が持ち込まれた各国の裁判所の考えに基づいてどの国の法律が適用されるかが判断されることになると考えてよいでしょう。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Jurisdiction(裁判管轄)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)
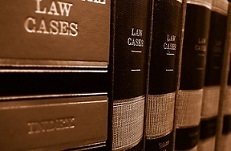
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Jurisdiction(裁判管轄)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約から生じる,または,本契約に関連して紛争の一切は,X国のX裁判所が第一審の専属的管轄を有することに当事者は合意する。」という旨が規定される条項です。
色々なバリエーションがあり,英文契約書では,「友好的(Amicably)に話し合いで解決できなかった場合には」,「衝突法の適用を排除する」,「あたかも両当事者がXの法人で有るかのように」云々などと付記される場合もあります。
このJurisdiction(裁判管轄)条項の狙いは,当事者が,仮に当該契約を巡って紛争になった場合,どこの国のどこの裁判所で裁判をすることにするのかについて予め合意により決定しておく点にあります。
そうでないと,クロスボーダー取引,国際取引では,2国間以上の国にまたがり当事者が存在しているため,どこの国の裁判所が管轄を持つのか,不明確になってしまうためです。
他方,当事者が英文契約書で裁判管轄について予め合意しておけば,多くの国では一定のルールの下,当事者の合意した裁判所に管轄権を付与することを認めていますので,一定の対策にはなるわけです。
もっとも,一部の国や裁判所では,当事者が合意によって管轄を決めていてもこれを退けることもあります。また,当事者のいずれも依拠していない第三国の裁判所などと決めていても,当該裁判所がこれを排斥することもあります。
英文契約書に管轄が書かれていない場合は,基本的に訴訟を提起した先の裁判所が自ら判断できる管轄権を有するかを判断することになるでしょう。
いずれにせよ,究極は当該裁判所の判断に委ねられているわけですが,事前に合意をしている場合とそうでない場合で,通常は大きな差があると考えてよいでしょう。
そのために重要な条項です。どちらの国の裁判所で紛争解決をするのかは重大な問題ですから,当事者のバーゲニングパワーで決められていることが少なくありません。
ただし,言うまでもないですが,自国の裁判所での管轄を合意できたとしても,裁判所での解決が現実的に意味があるのかということは別途考えなければなりません。判決で勝訴したとしても,相手国での強制執行を残す場合には,判決は絵に描いた餅になる危険があります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Arbitration(仲裁)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにArbitration(仲裁)条項があります。
これは,契約当事者間で契約に関して何らかの紛争が生じた場合に,(裁判ではなく)ADR(Alternative Dispute Resolution)(裁判外紛争解決手続)の一つである仲裁手続(Arbitration)に付するという合意のことです。
仲裁手続(Arbitration)は,その分野に詳しいとされる専門家たる仲裁人が当事者の間に入り,基本的には当事者の話し合いによる解決を尊重する手続きです。ただし,調停などとはことなり,当事者が話し合いにより和解できなければ,最終的には仲裁判断という判決に似た決定が出ます。
仲裁手続をするには当事者の合意が必要です。この合意は,必ずしも契約書締結の段階でする必要はなく,紛争に至ってから,当事者間で話し合い,仲裁手続によって解決することを合意し,仲裁に付するということも可能です。
ただし,紛争状態に至ってから,紛争解決手法を話し合うのは,現実的ではないことが考えられます。したがって,仲裁手続に付することを英文契約書で予め合意しておくことが主流となっています。
英文契約書における条項としては,「本契約に関する紛争は,X仲裁規則に従ってX国のX仲裁機関による仲裁手続により最終的に解決するものとする。」などと規定されます。
詳しい規定では,さらに,仲裁人の選定方法,人数,仲裁手続で使用する言語,上訴ができない旨の文言,仲裁人の費用の負担方法,仲裁判断には理由が付される旨の文言などが加わることがあります。
仲裁と訴訟の違いは色々とありますが,こちらの記事「英文契約書の準拠法と管轄」で解説していますので,ご覧下さい。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Termination(解除)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions)に,Termination(解除)条項があります。
この条項は,英文契約書で使用される場合,通常,どのような場合に契約を解除ができるか具体的な事由が列挙され,その事由に該当する事態になった時,どのような手続きで解除ができるかが書かれています。
英文契約書では,解除できる場合の事由については,例えば,①当事者が契約条項の内容に違反した時,②債務の履行を怠った時,③法律違反があった時,④支払不能・破産状態に至った時,⑤破産手続きなどの法的手続きが開始された時などと規定されること多いといえます。
また,どのような手続きで契約を解除できるかについては,大きく分けて,①無催告解除と呼ばれる手続きと,②催告解除という手続きと2通り存在します。
説明の便宜上,②の催告解除から説明しますと,こちらは,例えば,相手方に契約違反があっても,すぐに解除はできず,一旦その契約違反を一定期間内に治癒しなさい(例えば,2週間以内に代金を払いなさい)という通知を出して,その期間内に相手が契約違反を治癒しない(2週間経っても代金が支払われない)場合に,今度は契約を解除する旨の通知を出してはじめて解除ができるという場合を指します。
このいわば猶予期間を設ける趣旨は,銀行の送金エラーがあったり,単に経理の処理ミスで支払いを失念していたりということがありうるので,これらのためにという側面があります。
これに対して,①の無催告解除は,例えば,相手方に契約違反の事実があった場合,他に何らの手続きも要さず,単に「契約を解除する」と相手方に通知をすれば直ちに解除できるというものです。
これは,相手方が倒産状態に至った場合などを想定して,英文契約書でよく規定されます。倒産状態に至った相手に一定期間内に履行しなさいという催告は無意味な場合が多いでしょうし,当事者としては倒産状態にある相手方に対する自分の債務から早く解除によって解放されたい動機があるためです。
英文契約書における契約解除条項は,重要な条項ですので,どのような場合にどのような手続きで解除できるのか,解除した場合の効果はどのようなものか,事前にしっかりと吟味してから契約書にサインする必要があります。
Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by providing notice in writing to the other Party if the other Party:...(相手方当事者が下記の事由に該当したときは,いずれの当事者も相手方当事者に書面で通知することにより,即時に本契約を解除することができる) などと規定されます。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Intellectual Property Rights(知的財産権)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)
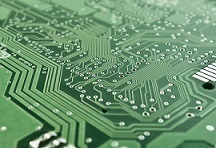
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Intellectual Property Rights(知的財産権)条項があります。
例えば,英文契約書のうち,販売店契約(Distributorship Agreement)などで,販売店が自国で商品を販売した際に,第三者の知的財産権を侵害しないことを,サプライヤー側が補償するなどと規定されることがあります。
これは,The Supplier shall indemnify and hold harmless the Distributor from any claims...by a third party alleging that use or sale of the Products infringes its intellectual property rights...(サプライヤーは,本商品の使用または販売が,知的財産権を侵害すると第三者が主張してきた場合,販売店に対し補償し損害を与えない…)などとして規定されることになります。
反対に,サプライヤーは,販売店による商品の使用または販売による第三者の知的財産権の侵害可能性について一切補償せず,これらを販売店のリスクにするという英文契約書もあります。
この場合は,The Supplier shall not indemnify or hold harmless...として補償しないという否定形に規定されることになります。
更に進んで,上記のような場合に,今度は販売店がサプライヤー側を補償するという条項も英文契約書に見られます。自国での販売なのだから,当該商品による自国での知的財産権侵害の可能性については販売店が全責任を負うべきだという発想です。
この場合は,英文契約書では,The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier...として,立場が逆転して規定されます。
知的財産権の侵害については,大きな問題に発展する可能性がありますので,そのような場合にどちらが責任を負うのかについて英文契約書に明示しておくことで,当事者の対処すべき課題を明らかにすることができます。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Conferral with Counsel(弁護士への相談)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Conferral with Counsel(弁護士への相談)条項があります。
例えば,英文契約書で,「両当事者は,本契約の内容と効果について,資格を有する弁護士に相談し,これらを理解したことを表明し確認する。」などという内容で規定することがあります。
これは,英文契約書にサインした後に,当事者が「サインの時は,英文契約書の内容をよく理解していなかった。この条項はかくかくしかじかの説明を受けていたから,かくかくしかじかの意味だと勘違いしていた。そのため,その条項は無効だ。」などと主張できないようするという狙いがあります。
こうした,勘違いによる契約の無効主張は,日本法では「錯誤」(さくご)と呼ばれており,コモンローの考えでは,mistakeという概念で規律されています。
このような条項が挿入された英文契約書のドラフトを受領した場合は,通常の場合以上に,弁護士などの専門家に相談する必要性が高いと言えるでしょう。
Conferral with Counsel条項があるにもかかわらず,弁護士などへ相談せずにサインし,その後,内容を勘違いしていたと説明して錯誤による無効などを主張することは不可能または極めて困難となると考えられるからです。
なお,英文契約書でConferral with Counsel条項を設けなければ,錯誤無効やmistakeの主張を封じられないということではありません。
つまり,このような条項がない契約書に,弁護士などに相談せず内容をよく理解しないままサインした場合は,後で錯誤(mistake)により無効だと主張することができるということを必ずしも意味しないので,注意が必要です。
契約書にサインをしてしまうと,原則として,その後,「勘違い」,「誤解」を理由として英文契約書の効力を否定するのは極めて困難であることは理解しておく必要があります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Survive(存続)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Survive(存続)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,一般的に,「本契約が解除または期間満了により終了しても,第XX条,第XX条及び第XX条は,なお有効に存続し,当事者を拘束する。」などという内容で規定されます。
英文契約本体が期間満了などにより終了した場合,その英文契約に規定された各条項は基本的には効力を失うもの(例えば,商品の引渡義務や代金支払義務)が多いですが,なお効果を存続させたい内容の条項も多く存在します。
これら英文契約が終了してもなお効力を存続させたい条項をSurvive(存続)条項に列挙することがあります。
効果が存続すると規定される代表例は,Confidentiality(守秘義務),Non-Competition(競業避止義務)や,Non-Solicitation(勧誘禁止義務)の他,Arbitration Agreement(仲裁条項)やGoverning Law(準拠法)などの一般条項です。
その内,Confidentiality,Non-Competition,Non-Solicitationなどは,契約終了後も永遠に効果が生じるとすると,準拠法によっては,当該条項が規制する効果の範囲が広すぎ妥当でないとして,無効とされる場合もあります。
その他,この種の条項は,存続期間が長すぎるという場合,裁判所により,ケースバイケースの判断で,当事者間の不公平や職業選択の自由に対する制約になるなどを理由に無効と判断されることもあるので,条項設定時には注意が必要です。
このような観点から,英文契約書のConfidentiality条項などには存続期間を入れる場合もあり,その場合,Article X shall survive termination or expiration of this Agreement regardless of the reason for five (5) years from such termination or expiration.(第X条は,理由を問わず,本契約の終了又は解除から5年間存続する。)などと定めることになります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Indemnification(補償)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック,翻訳する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)にIndemnification/Indemnity(補償)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「いずれの当事者も,本契約の義務の履行に基づき,または,本契約に関連して,相手方当事者が第三者からクレーム等を受け,損害もしくは費用(合理的な弁護士費用を含む)を被り,負担したときは,これらについて相手方当事者を補償する」などという内容で登場します。
上記は,当事者のいずれもが相手方を補償するという内容になっていますが,いずれかの当事者のみが相手方を補償するという内容のものもよく見られます。
一方のみが相手方を補償するという内容は,「不公平」のように見えますが,履行義務の内容・性質,当事者間の力関係(Bargaining Position)などによりそのような内容になることがあります。
こうした英文契約書のIndemnification/Indemnity(補償)条項の内容を検討する際には,実際に補償することになるリスクの程度・内容,保証するとなった場合の保証の内容・範囲などを吟味して条項の正当性について検討する必要があるでしょう。
補償の内容・程度としては,英米法圏の契約書ですと,Defendという英文契約書用語が書かれていることもよくあります。
これは,相手方が第三者と紛争や訴訟となった時に,補償する当事者が弁護士を選定して自らの費用負担で防御し,解決にあたるということを意味することがあります。
また,補償を受ける方当事者側に過失が認められるようなケースはどのように扱うかなども重要な検討事項と言えるでしょう。
以上のように,英文契約書のIndemnification/Indemnity(補償)条項は,検討すべき事項の多い重要な条項と言えます。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Disclaimer(免責)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにDisclaimer(免責)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本製品は…の状態で引き渡されるもので,本契約に明示的に定められた場合を除いて,本製品の契約不適合(瑕疵)等について売主は一切責任を負わない」などと定められます。
英文契約書における本条項の狙いは,言うまでもなく,当事者の責任を免除したり,一部に限定する点にあります。
製品の英文売買契約では,As is basis(現状有姿)で引渡し,製品に何らかの欠陥があったとしても売主は責任を負わないという条項を入れることがあります。特に中古品の売買で多く見られる規定です。
この場合は,Disclaimer(免責)条項が挿入され,仮に製品引渡し後に問題が生じたとしても,買主の責任と費用負担で対処することが決められることが多いです。
このDisclaimer(免責)や,Limitation of Liability(責任制限)を英文契約書で定めるときは,注意が必要です。準拠法によっては,無効と判断されてしまう場合があるからです。
コモンローでも,一定の場合,目立つ表記で書かれていないと無効になるというルールがあります。
英文契約書をドラフトする,チェック,修正する場合,常に自分の側が有利になるようにすれば良いというものではありません。有利と思って作った条項が強行法規/強行規定や判例に違反して無効になったり,相手に有利な解釈にされてしまったりすれば逆効果になりかねません。
英文契約書は,あくまで,適用法令・慣習を異にする2つ以上の当事者が,それぞれの利益を調整し,リスクをヘッジしながら,妥協点を見て合意するものであると(一方が他方に押し付けるというものではない)いう大前提を忘れてはいけないということでしょう。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Anti-Bribery(反賄賂)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Anti-Bribery(反賄賂)条項があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「当事者のいずれも,適用法令に違反するいかなる賄賂の収受を行ってはならない」という内容で規定されえます。
Anti-Bribery条項に違反すると,Material Breach of Contract(重大な契約違反)となると規定されることもよくあります。
賄賂の収受に関する規制法は各国によって相当に異なることに注意が必要です。例えば,私が3年ほど留学していたイギリスでは,賄賂は公務員以外に供与しても贈賄にあたりますし,日本法に比べて相当に厳しく,広い規制がかけられています。
また,日本の駐在員などが,それと気づかずに贈賄行為を行い,途上国などで身柄を拘束されていますという事例も珍しくありません。
英文契約書に賄賂の収受を禁ずる条項があるか否かにかかわらず,賄賂規制などの法令に関しては取引相手国における規制内容についても精査し,間違ってもこれに違反することのないようにしなければなりません。
新興国などにおける営業において,営業担当者が,「ある金員を支払わないと話が先に進まない,皆払っている」などとして,本社にある金員の支払いについて許可を求めてくることがあります。これについては法務としては,リスクが高すぎますので許容できないと明確に対応すべきだと思います。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Non-Competition(競業避止)(弁護士による英文契約書によく見られる一般条項の解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Non-Competition(競業避止)条項があります。
これは,例えば,
①Distributorship Agreement(販売店契約)のような契約で,Distributor(販売店)が当該契約に基づき販売する商品と競合する(compete)する商品を扱うことを禁止する場面で使われたり,
②Employment Agreement(雇用契約)などにおいて,役員または従業員が,使用者である会社の事業と競合する事業を兼業したり,退職後も競合他社に就職したり,役員に就任したりすることを禁止したりする場面で使用されることが多いです。
特に,②の方で使用される場合には,準拠法によって様々な規制がかけられている可能性があるため,競業禁止の条項を設けたからといって,そのままの効果が直ちに期待できると考えない方が良いでしょう。
あくまで一般論ではありますが,②の禁止を入れる場合,退職後の競業禁止のほうがより厳しく有効性を判断される傾向にあります。
契約期間中であれば,その会社の業務に専念すべきということも一定の理があるでしょうが,契約終了後も競合他社での稼働を禁止されるとなると,規制が厳しすぎるきらいがあるため,有効性は厳格に判断されます。
また,どちらかというと,役員に対する規制に比べて,従業員に対する競業禁止のほうが有効性を厳しく判断される傾向にあります。
授業員は雇われている立場で弱い立場の場合が多く,転職するとすれば通常は競合他社に就職することが多いため,これを禁止されると職業選択の自由に対する制限が強すぎると考えられるためです。
もしこのような禁止規定を入れる場合,当然ですが,契約終了後一定の期間に限定することも検討すべきです。
永遠に禁止されるという規定が拘束力を有することはまずないでしょう。
また,契約終了の事由によって競合禁止をする場合としない場合に分けるということもあります。
例えば,その役員や従業員の過失で雇用契約等が終了することになった場合は,競業禁止規定が適用されるが,それ以外の場面では競業禁止規定は適用されないとすることがあります。
これにより,あくまで,当該役員や従業員に帰責事由があるときのみ競業が禁止されることになるので,合理性が増すと考えられます。
①の方では,例えば,The Distributor shall not import, export or sell products which may directly compete with the Products...(販売店は本製品と直接競業する可能性のある商品を輸入,輸出または販売してはならない…)などと規定されます。
②の方では,例えば,The Employee shall not be employed by any entity or individual competing with...(従業員は…と競合する法人または個人に雇われてはならない)などと規定されます。
こうした規定は,当然のことながら,義務を課される側にとっては大きな不利益となる可能性があるため,条項を定めるか否か,定めるとしてもその内容について慎重に検討すべきと言えるでしょう。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Singular to Include Plural(単数は複数を含む)(弁護士による英文契約書によく見られる一般条項の解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにSingular to Include Plural(単数は複数を含む)があります。
ご存知の通り,英単語には単数形と複数形が存在します。そのため,英部契約書を作成していると,ある英単語が,単数形で書かれたり,複数形で書かれたりということがあります。
この場合に,単数形が使用されているから,1つに適用されるのであって,複数の場面を想定していないはずだなどの解釈上の紛争を避けるために入れられる条項です。
通常は,「本契約において,単数形か複数形かが使用されていても,文脈に応じて,両方を含むものとする。」という趣旨の意味で条項が挿入されます。
どちらかというと誤解を避けるために挿入するという条項のため,それほど重要性が高いというわけではないですが, 英文契約書特有の条項といえ,意味は理解しておいた方が良いでしょう。
似たような趣旨で挿入する条項としては,性別を区別しないという趣旨を記載する条項があります。例えば,heやsheなどと英文契約書に書いてあったとしても,heはsheを含むし,sheはheを含む,つまり,性別を区別しないというような条項が挿入されることがあります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Term(契約期間)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Term(契約期間)条項があります。
これは,概ね次のような内容になっている場合が多いです。
「本契約は,X年X日から効力を生じ,X年X日に終了する。」または「本契約は,本契約書に署名した日から,X年間有効である」などと規定されます。
契約期間は,当然ですが,非常に重要です。例えば,販売店契約(Distribution Agreement)や代理店契約(Agency Agreement)などでは,一般的に,特に最低購入数量の条件がなければ,販売店・代理店側は契約期間を長くとりたいでしょうし,反対に,サプライヤー側は,新規の販売店や代理店のパフォーマンスがわからないため,あまり長期間の契約は結びたくないというのが通常でしょう。
また,契約期間が満了した場合に,更新があるのかについても契約書に記載されることが通常です。例えば,自動更新を定める場合は,「契約期間満了日の3か月前までに,一方当事者が相手方当事者に書面により更新拒絶を通知した場合を除き,本契約は自動的に1年間更新されるものとし,以降も同様とする。」などとされます。
サプライヤー側からすれば,安易な自動更新は避けたいでしょうし,販売店・代理店からすれば,マーケティングコストなどの回収のため,相当期間は,更新して販売活動を続けたいと考えるでしょう。このあたりのバランシングが必要となってきます。
また,契約期間が満了し,更新もない場合,販売店・代理店としては,これまでの投下資本の回収の問題もありますし,自身が培った販路やブランド価値などを維持したいと考えます。この点の補償の問題をどう取り扱うかについても,重要な問題ですので,英文契約書を作成する際には,注意が必要となります。

英文契約書に関するサービスに関するお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまでは料金は一切かかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
Definitions(定義)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する一般条項に,Definitions(定義)条項があります。
日本語の契約書では,一部の契約書類系を除きあまり見ることがないですが,英文契約書では,頻繁に登場する条項です。
最初に定義条項が置かれていることもありますし,最後に置かれていることもあります。
英文契約書に限りませんが,契約書は,当事者が合意した内容を書面に書き記すものですから非常に大切なものです。
そのため,当事者に誤解が生じたり,英文契約書を読んでも内容が数通りに読めるたりするなどという事態は極力回避しなければなりません。
そのため,英文契約書で使用する用語を,きちんと定義し,その用語にあいまいな点を残さないようにすることが重要になるのです。
特に,英文契約書では,異なる法律や文化に存在している企業が契約に入るため,国内の企業同士の契約よりも,上記の誤解や解釈の相違というものが発生しやすくなります。
そのため,和文契約書よりも,英文契約書における定義条項の意義は大きいといえるでしょう。
これを定義しなければならないということが特にあるわけではないですが,英文契約書に複数回登場し,一義的に意味が明らかにならない(解釈が複数成り立つ,あいまいなのでどれが該当し該当しないかがわからない)場合には,定義をしておいた方が良いと思います。
また,一般条項として別に定義条項を入れる場合だけではなく,英文契約書の条文中で各用語を定義していくという方法もあります。
この方法は,読みにくくなる(定義を読むながらあとで参照しづらい)という欠点もあるので,定義すべき用語が多い場合は,Definitionsという一般条項を別に入れたほうが良いと思います。
用語を一度定義したら,必ず同じ意味で,同じ表記(通常は最初の文字が大文字)を使用することが大切です。
わざわざ定義をしたのに,小文字で使用したり,類似の別の表現をとったりすると,それは違う意味であるから別の表記をしたのだと解釈に争いが生じる危険があります。

英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。
正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。
原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
お問合せ・ご相談はこちら
お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。
お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。
担当:菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
片山法律会計事務所
住所
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
アクセス
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日
士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。
ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。
ご相談方法
メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。



