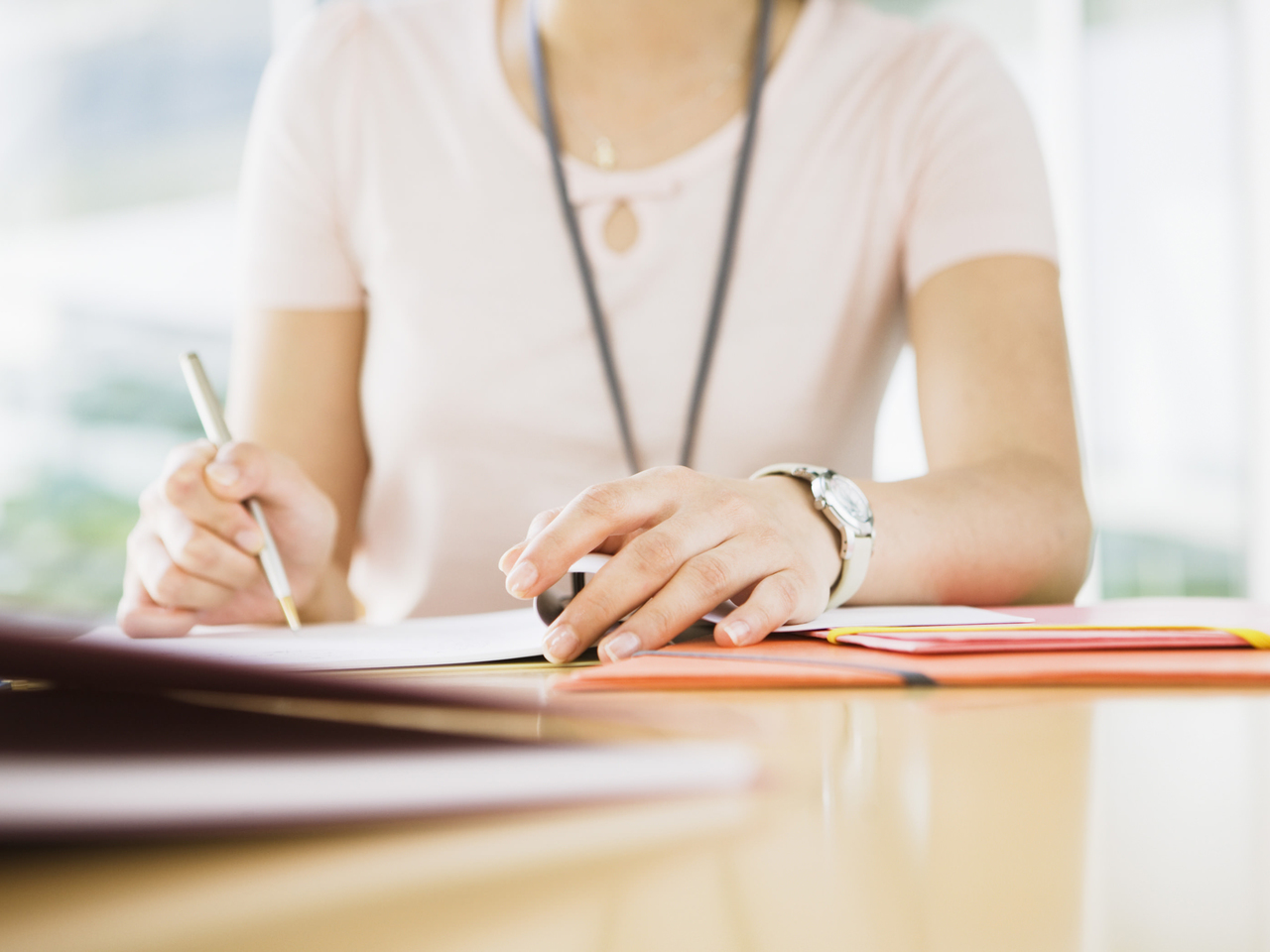英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Provided that...,/provided, however, that...があります。
Provided that.../provided, however, that...は,英文契約書で使用される場合,通常,subject toと同様の意味であり,「ただし…である場合に」という意味を持っています。
つまり,that節以下の文章が,但書,条件を意味していることになります。
原則的な内容の条項を定めた後に,その例外を定めたいときに,但書として,provided that.../provided, however that...を使って規定します。
そのため,provided that.../provided, however, that...という表現が出てきた場合,that以下に書かれた内容が本文に書かれた内容よりも優先されると理解すると理解しやすいと思います。
例えば,The Seller may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the Distributor at least thirty (30) days prior to the expected termination date; provided, however, that...(売主は,終了予定日の30日前までに販売店に通知すれば,いつでも本契約を解約することができる。ただし・・・)などと使用されます。
こういう表現がされている場合,provided, however, that...の...の部分に書かれている内容を成就させないと,本文で認められている契約の解除権が発生しないということになります。
つまりは,本文の内容よりもthat以下の内容が優先する,that以下の内容が前提となることを意味しているのです。
したがって,英文契約書をレビューする際には,provided that...の後に何が書かれているか,但書の内容を正確に把握しておくことは非常に重要です。
That節の中に書かれている内容が優先されるのですから,原則が書かれている,providedの前の内容を見て納得できたとしても,that以下に書かれている内容が,自社にとって現実的に実行することが難しいという場合は,その条項はそのままでは受け入れられないということになります。
なぜなら,いくら本文中に自社に有利な内容が書かれていても,provided以降に書かれている内容の実現可能性が乏しいのであれば,本文中の有利な内容は絵に描いた餅にすぎず,結局規定されている意味がないということになりかねないからです。
ちなみに,英文契約書を作成,チェック(レビュー),修正する際に,このprovidedを使用した表現は非常に便利です。
理由は以下のとおりです。
例えば,契約書をチェック,レビュー/審査している際に,「この条項は自社に不利益が大きいから受け入れられないな。」と判断したとします。
この場合に,その条項を契約書から削除するように求めるのが最も直接的です。
ただ,相手方も,その条項を貴社に守ってほしいから挿入してきています。
そのため,ただ単に削除してほしいと依頼しても,削除は受け入れられないと回答され,交渉が平行線をたどるということになりかねません。
その際に,有効なのは,単に削除するのではなく,本文の内容は生かしたまま,provided that.../provided, however, that...という条件を加えるという方法です。
本文に書かれた内容が受け入れがたくとも,Provided that.../provided, however, that...を挿入し,thatの中に自社が許容できる条件内容を入れ,それが充たさせれた場合には,本文の内容を受け入れても良いという場合には,条項自体は残しつつ,実質,本文の効果を削減することができます。
例えば,本文中に書かれている義務を貴社(売主)としては実行するのはかなり困難を伴うとします。
その場合,provided that.../provided, however, that...を本文の後に加え,そのthat節中に,「ただし,買主と売主が協議し,売主が同意した場合に限る。」という内容になるように文章を入れます。
そうすれば,本文の内容は貴社が同意しない限りは義務ではないことになり,実質義務を自社の意思次第により無効化できるということになるのです。
もちろん,このような露骨な修正は,相手も気づくことが多く,こううまくは運びませんが,このように提案してみると,相手方も,具体的に文言の内容を検討するようになることがあります。
そうすると,例えば,相手方も,「同意がいると言われれば,売主が拒否すれば良いだけなので,それでは義務とはいえないので,受け入れられない。せめて,合理的な理由なく売主は拒絶はできないという文言を加えさせて欲しい。」などと提案してくるかもしれません。
こうなれば,最初の状態よりは事態は改善しています。
なぜなら,最初は問答無用で売主の義務であったのが,不合理な理由でその義務を行なわなければならないときには,売主は義務の履行を拒絶できることになるからです。
もちろん,これでも,何が合理的な理由なのかなどのあいまいさは依然として残ります。
ただ,最初の原案では,義務の履行を求められた場合,売主としては拒絶する理由がなかったところ,修正案では,「その理由は合理的ではないので,今回は履行義務を負わない。」などと根拠をもって反論できる余地が生まれたといえます。
そのため,オリジナルの内容よりは自社に有利な状態に改善できたといえるでそふ。
このように,provided that.../provided, however, that...は,英文契約書をチェック,レビュー/審査,修正する際に非常に使い勝手が良い表現といえます。
他にも,subject to...という表現もprovidedと同様に,但書の役割を果たします。
Subject to...の…の部分に来る内容が優先されます。Subject toについての解説記事はこちらで読めます。