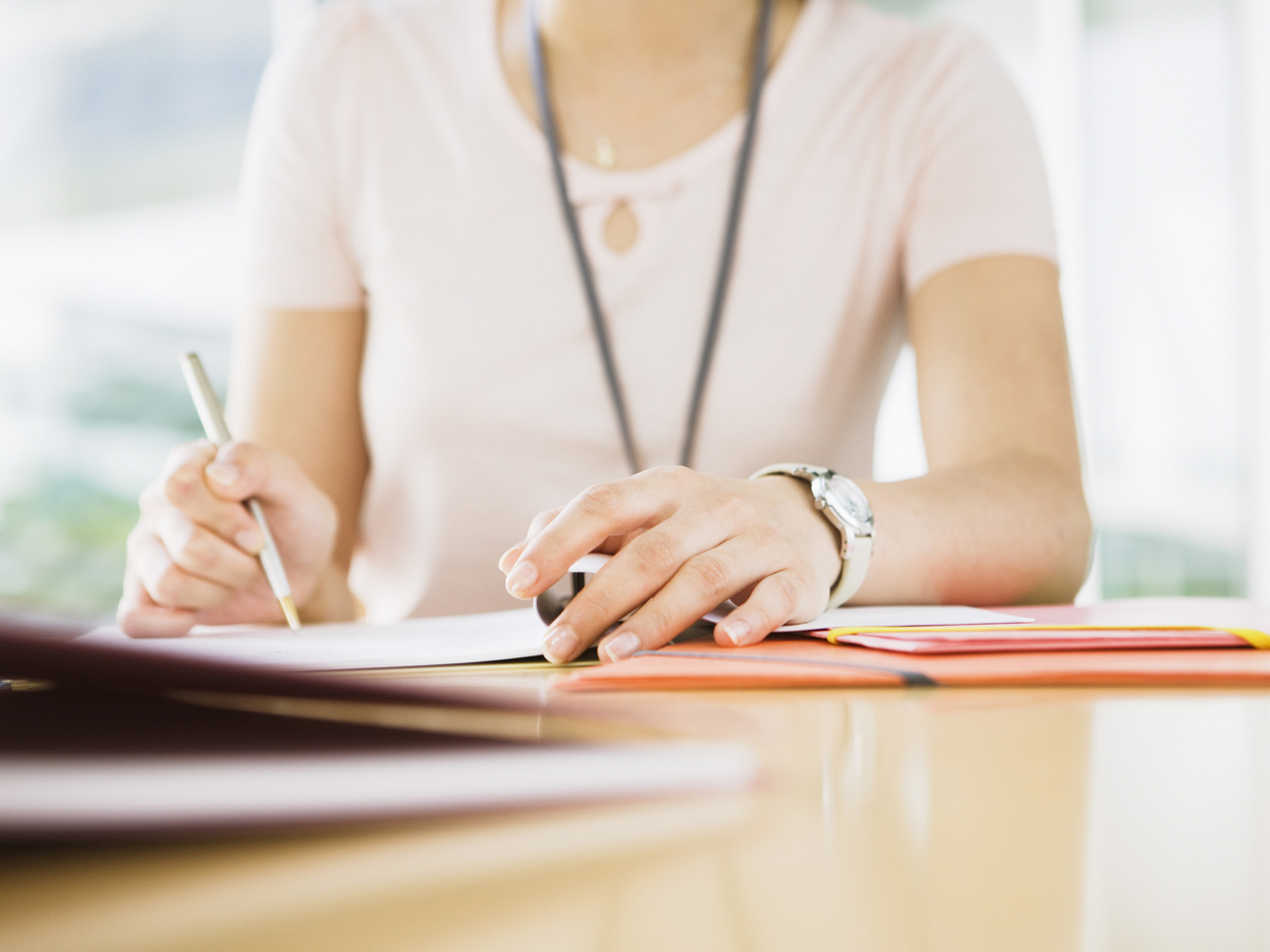英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Be responsible for.../be liable for.../be obliged to do/have a duty to doがあります。
これらの英文契約書用語は,英文契約書で使用される場合,通常,いずれも,「…について責任・義務を負っている,…する責任・義務を負っている」という表現です。
例えば,The Distributor is responsible for any expenses incurred by itself during the performance of the Service...(販売店は,本サービスを提供する際に自社にかかる一切の費用について負担する)などと使用されます。
Responsibleという表現が出てきた場合,誰が費用などを負担するかについて規定されているような場合が多いため,この用語の前後の内容は非常に重要である場合が多いと言えるでしょう。
ちなみに,liableとresponsibleは,日本語ではどちらも「責任があると」訳されることが多いですが,両者の違いは,前者が法的責任を表していて,後者は法的な責任のほか道義的な責任も含んでいると考えられています。
どちらかといえば,契約書では法的責任を問題にするので,liableのほうがよく使われるといえるでしょう。
なお,liableとresponsibleは「責任」を表しているのに対し,obligedやdutyは「義務」を表しています。
ここで「義務」と「責任」がどのように異なるかですが,「義務」に違反した場合に生じるのが「責任」ということになります。
もっとも,英文契約書ではこの点を厳密に区別して書かれているとは言い難いところがあります。
ですが,一応,義務が先にあって,その義務に違反した場合に生じるのが責任であるということは覚えておくとよいでしょう。
なお,「…する義務がある」「…しなければならない」という義務を表す表現で最も一般的で英文契約書に頻出する用語は,be obliged to doやhave a duty to doではなく,shall…という表現です。
Shallは英文契約書で義務を表す場合に最もよく使用される典型的な義務を表す用語です。
Willも義務を表す表現として登場しますが,willはshallよりも義務の程度が弱いと解く方もいらっしゃるので,より好まれるのはshallといえるでしょう。
Shallとwillの解説記事はこちらです。
ちなみに,mustやshouldという表現も英文契約書でたまに見かけますが,基本的に義務を表す表現としてmustやshouldを使うのは避けたほうが無難です。
特に,shouldを使うと,法的義務ではなく,「…したほうが良い」という提案的な内容だと解釈される可能性が高まるので,気をつけて下さい。
英文契約書を作成する最も重要な目的の一つが当事者の権利義務をを規定することですので,当然ですが,英文契約書で義務を表す表現は最も大切な部類に入ります。
そのため,誤解がないよう,確実に義務だとわかる表現を使う必要があります。
義務を表す表現はshallを使用すれば間違いはないでしょう。
ただ,英文契約書を読んでいると,他にも義務を表す表現が登場することがあります。
例えば,be required to doという表現も義務を表す表現として英文契約書に登場します。
これは文字どおり,「…することが要求されている」=「…しなければならない」という義務を表しています。
また,少し毛色の異なる表現として,agree to doも挙げられます。
これは,直訳すると「…することに同意する」という意味になり,転じて「…しなければならない」という義務を表すことになります。
よく,英文契約書でacknowledge and agree that...という表現を見ると思うのですが,このagree that...というのも,that以下の内容について同意してるので,義務を表すことがあります。
単にacknowledgeだけだと,that以下の内容を「確認する・認める」という意味にとどまり,必ずしも義務を表したものではないと解釈されることがあるので,acknowledgeを使う際には注意したほうが良いでしょう。
このように,契約書において義務を表す表現は数多くあります。
ですが,小説などの文学性がある文章とは異なり,契約書においては,表現が豊かであれば良いということではなく,内容が一義的に明らかで正確であることが何より大切です。
そのため,義務表現をいろいろな言い方で変えるということはせず,shallを使用するなら,shallを最初から最後まで統一的に使用することをおすすめしています。