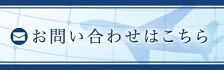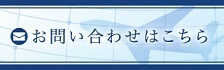英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,Be attributable to...があります。
Be attributable to...は,英文契約書で使用される場合,「…に帰責しうる」という意味です。
例えば,「X is liable for the damage that is attributable to its fault」というように使用されます。
これは,和訳すると「Xはその過失の限度で損害についての責任を負う」という意味になります。
日本法の下では,債務不履行責任を問うには原則として債務不履行した当事者に「帰責性」「帰責事由」が認められることが必要とされています。
そして,この帰責性は,英文契約書ではattributableという用語で示されることが多いです。
英米法の下では,契約責任を問うのに,日本法のような帰責性は原則として要求されていませんので,英米法などを基礎にした英文契約書では,このような表現はあまりしません。
どちらかというと,日本的な表現と理解しておいて良いでしょう。
もっとも,準拠法(Governing Law)が日本法以外の国の法律となっている場合でも,attributableという表現が登場することはあります。
その場合もやはり債務不履行・契約違反の責任を追及するためには,その原因が債務不履行・契約違反をした当事者の責めに帰すべき事由であることが必要という文脈で使われることが多いです。
損害賠償などの責任を負う要件として,このような当事者の帰責性が必要かどうかは,重要な意味を持ちます。
帰責性がなくても責任を負うことになれば,無過失であっても契約違反があれば責任を負う可能性があるため,責任が重いです。
これに対し,債務不履行責任に当事者の帰責性が必要となれば,注意をしていれば損害賠償責任などの責任を負うことを回避できるのですから,無過失責任に比べて責任は軽くなります。
そのため,英文契約書を審査する際には,損害賠償などについて記載された条項(補償条項:Indeminity/Indemnification Clause)がどのような内容になっているか,帰責性の必要性などを必ずチェックするようにしましょう。
また,不可抗力(Force Majeure)により債務不履行が生じた場合に免責があるのかもチェックするようにしましょう。
損害賠償に関する条項には,attributableというような用語がなくても,不可抗力免責があれば,実質的に債務不履行に帰責性を要求するのと同じ効果が生じるためです。