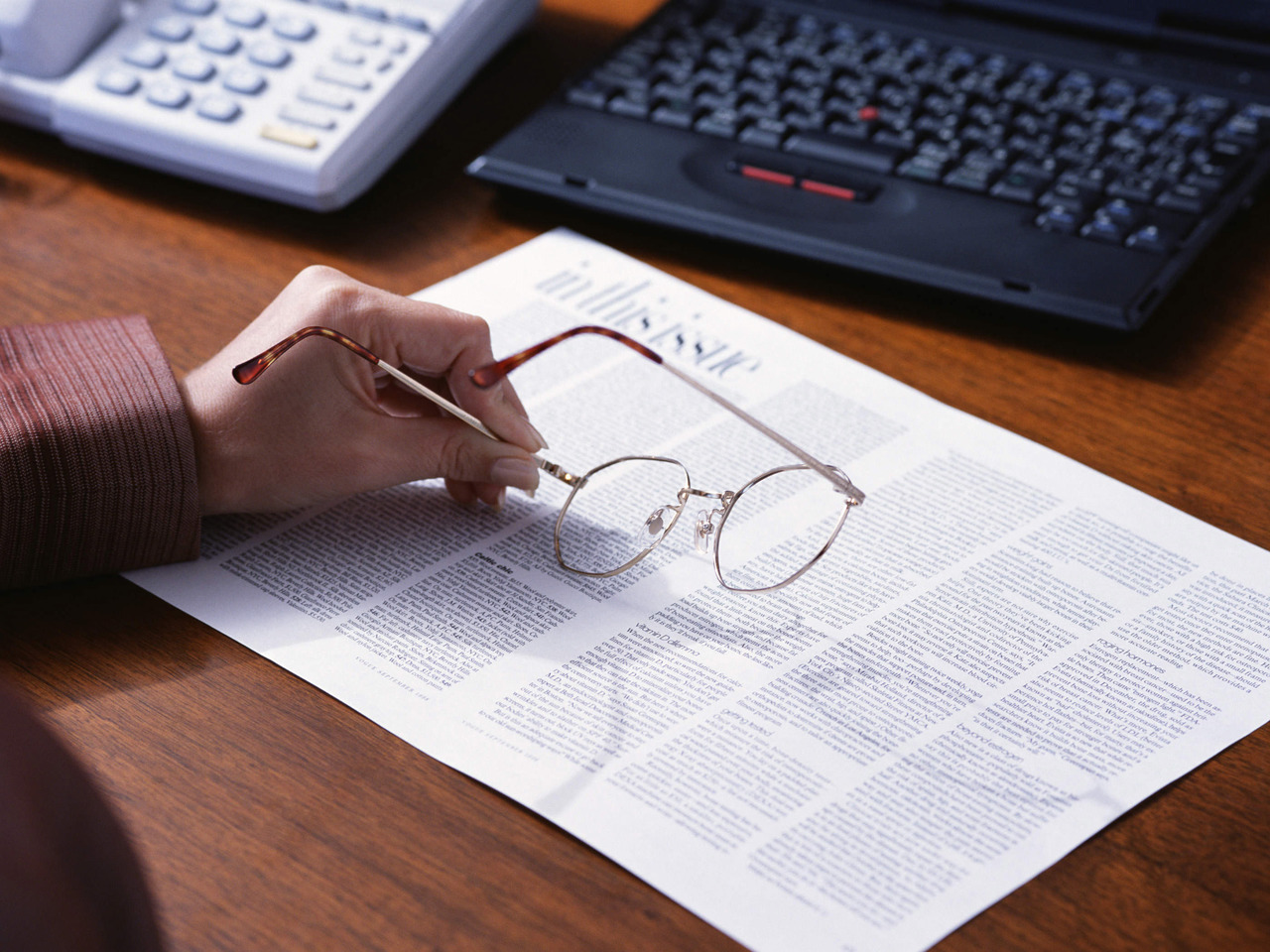英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Renewがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,「契約の更新」を意味することがよくあります。
基本取引契約(Basice Sales Transaction Agreement)などで,継続的な売買などが予定されている契約の場合,当該基本契約の更新条件は重要です。
どのような場合に更新が可能なのか,更新する際の手続きはどのようなものか,更新後の条件はどのような内容かなど,十分に検討しなければなりません。
例えば,The initial term of this Agreement shall be for two (2) years from X, and shall thereafter be automatically renewed for successive one (1) year extension periods unless terminated by either parties by giving written notice of termination to the other at least thirty (30) days in advance of the following renewal date.などと使用されます。
なお,上記の日本語訳は,「本契約の当初の期間は,X日から2年間とし,その後は,いずれかの当事者が相手方に対し,契約の更新日より30日前までに,更新をしない旨を通知しない限り,1年ずつ自動更新される。」となります。
ちなみに,一般論としては,例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,販売店側としては,ノルマになる最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)などが定められていないのであれば,投下資本回収の側面もあることから,長期間の契約を望む傾向にあります。
他方,サプライヤー側は,最低購入数量(ノルマ・ミニマム)がないのであれば,販売店(Distributor)のパフォーマンス次第では,契約を終了させることを考えたいため,契約期間は短く刻みたいと考える傾向にあります。
また,反対に,上記例で,最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)が定められていて,毎年ノルマの数量が上がるなどの場合,販売店としては,短く刻んで,更新拒絶がありうる状態にしておきたいと考えでしょう。
その一方,サプライヤーとしては,今度は上方修正の最低購入数量(ノルマ・ミニマム)が定められていて利益は確保できる以上,それなりの期間契約してもらうことを望む傾向にあります。
ちなみに,自動更新にすると,更新拒絶の通知(Non-renewal Notice)をしない限り自動的に契約が更新されることになりますので,当然ですが当事者が更新を期待する度合いが高くなります。
何もしなければ契約が自動的に更新されるということは,契約が更新されるのが通常の状態と考えるためです。
そのため,仮に契約期間が1年間などと比較的短めに設定されていても,契約当事者は「自動更新が定められているし,まさか1年間で終了することはないだろう」と考えがちです。
こういう場合に,短期間で更新拒絶をすると,トラブルに発展しやすいので注意が必要です。
逆に,更新については契約書に記載せず,期間満了で一旦終了することを前提にした契約書を作成すれば,ひとまず契約は終了することを互いに認識しているので,自動更新条項よりは契約終了時に揉める可能性は低くなります。
この場合でも当事者がお互いに更新を望み新たに契約を結んだり,更新することを合意したりすれば,当然契約関係を継続することが可能です。
したがって,自動更新ではなく一旦は契約が終了するとしておき,終了前に条件を再度交渉してお互いが納得した場合にはじめて再度契約ができるとしておいたほうが,更新への期待を少なくできますし,納得してはじめて契約が継続するので安全といえるでしょう。
契約の終了時は最もトラブルになりやすいタイミングの一つですので,契約終了関しては慎重に進めることを強くおすすめします。