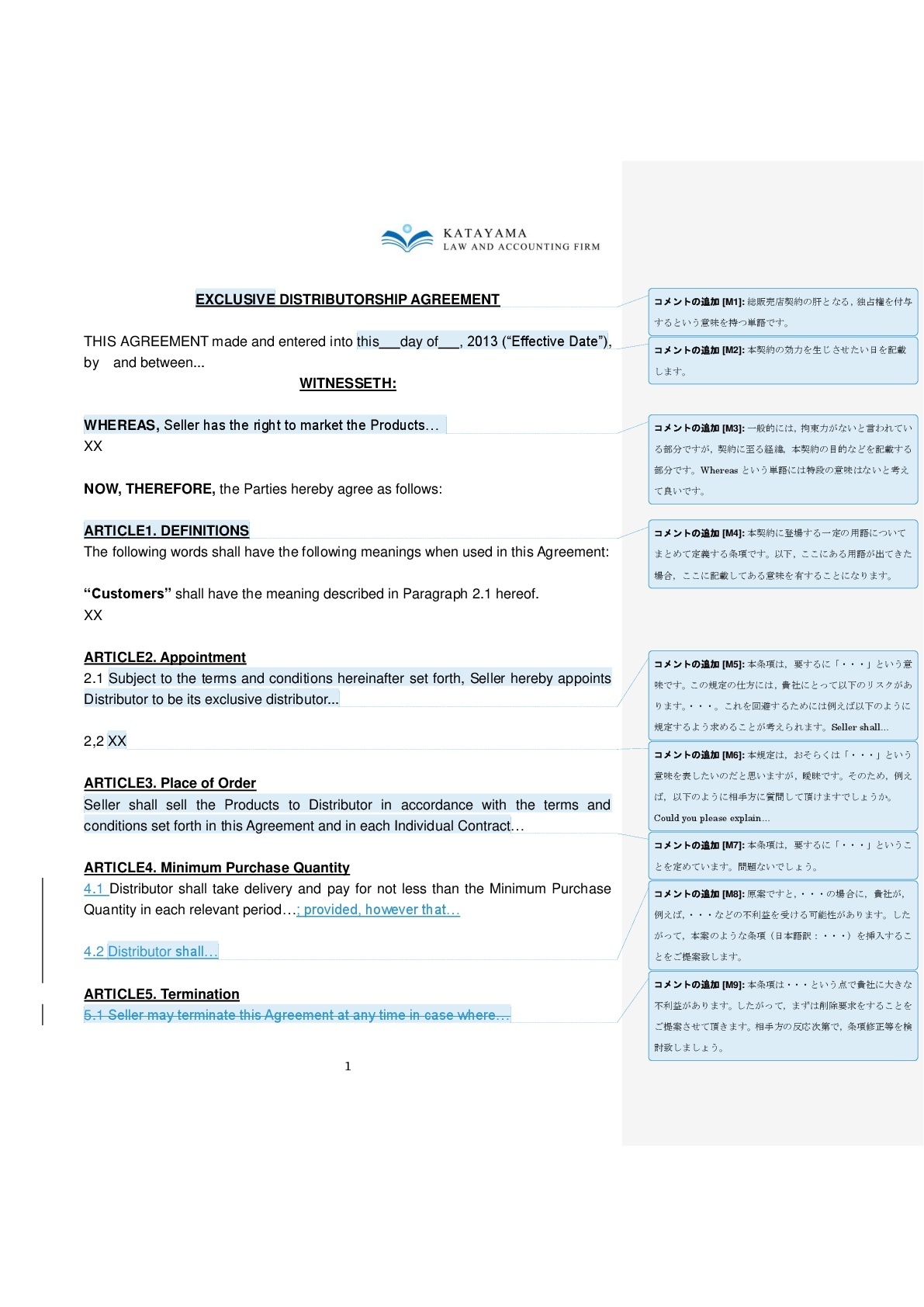英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際に,「海外のサプライヤーが制裁対象(Sanctioned Entity)に指定された場合,契約を解除できますか」というご相談をいただくことがあります。
米中関係の緊張が再燃する中,米国による制裁指定(例:Entity List指定)や関税強化措置(いわゆる「トランプ関税」)が再び注目されています。
こうした地政学リスクの影響を受ける可能性がある国・企業と取引を行う場合,英文契約書において事前にリスク対応策を講じておくことが重要です。
制裁対象となった場合の実務上のリスク
たとえば,日本企業が中国企業から部品を調達し,その完成品を米国や欧州に輸出しているとします。
この中国企業が米国の制裁対象リスト(Entity ListやSDN List)に追加された場合,以下のような問題が発生します。
-
米国・欧州への再輸出が規制され,輸出不能となる
-
製品全体が「制裁対象企業の部品を含む」と見なされる
-
買主側(日本企業)が契約を履行できず,納期遅延や違約金のリスクを負う
-
それにもかかわらず,契約上の解除権や免責条項が明示されていない
このように,制裁指定があっても契約義務だけが残るというリスクが現実に存在します。
有効な対応策:制裁条項(Sanctions Clause)
上記リスクに備えるには,英文契約書に制裁関連の条項(Sanctions Clause)を盛り込むことが実務的に有効です。
たとえば,以下のような条文が考えられます。
Sanctions Clause(制裁条項)例:
“If either Party becomes subject to any sanctions or export control restrictions under applicable laws, including but not limited to those imposed by the U.S., EU, or UN, the other Party shall have the right to suspend or terminate this Agreement immediately upon written notice, without any liability.”(和訳)「いずれかの当事者が,米国,EU,または国連によって課される制裁または輸出規制を含む適用法令に基づく制裁措置の対象となった場合,他の当事者は,書面による通知により直ちに本契約を停止または終了させる権利を有し,その責任を一切負わないものとする。」
このように書いておくことで,相手方が制裁対象となった場合に,違約責任なく契約を終了させることができます。
原産地変更リスクへの対応
制裁リスクだけでなく,「関税措置」や「原産地規則の変更」によって取引が困難となる場合もあります。
たとえば,「中国製」と判断された部品が25%の制裁関税の対象となり,輸入価格が急騰することがあります。
こうしたリスクにも,事前に原産地変更(alternative sourcing)に関する条項を設けておくことで対応可能です。
Origin Flexibility Clause(原産地変更条項)例:
“If any change in applicable trade laws or regulations results in material tariffs or restrictions applicable to the country of origin of the Products, the Supplier shall, upon Buyer’s request, promptly propose an alternative country of origin, subject to Buyer’s approval.”(和訳)「適用される貿易法または規制の変更により,製品の原産国に対して重大な関税または制限が課される場合,サプライヤーは,買主の要請に応じて,買主の承認を条件として,速やかに代替の原産国を提案するものとする。」
このような条項を設けることで,調達先の変更や代替生産ルートへの切り替えが,契約上の協議義務として機能するようになります。
まとめ:地政学リスクは「契約」で先回りする
地政学的リスクは予測不可能ですが,契約書に反映しておくことで実務的なコントロールが可能になります。
制裁指定や原産地問題によって,契約が履行不能になるリスクは,実際の現場で頻発しています。にもかかわらず,「契約に書いていなかった」ために,泣き寝入りや損害賠償請求につながる事例もあります。
英文契約書のドラフトやレビューにおいては,価格・納期・数量といった目に見える条件だけでなく,リスクが現実化したときに何ができるかを事前に想定し,明文化しておくことが重要です。
制裁条項や原産地対応条項の有無が,将来の事業継続性や損失回避の鍵を握ることを,ぜひ意識して契約を設計していきましょう。